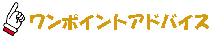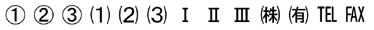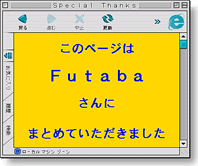
![]()
■ホームページ
■メールマガジン
■コミュニティの場
−−掲示板・チャット・ML
■電子出版
| ホームページ |
| ホームページをつくるということ ◎ホームページのメリット 1.地域も年代も超えた、全世界の人たちへ情報を発信できる。 2.パソコン上で作成したデータを印刷せずに配信できるため、 経費が抑えられる。 3.伝えたい情報をリアルタイムで配信できる。 4.ユーザーとのコミニュケーションの場が生まれる。 5.ミニコミ発行者同士のつながりができる。 ◎ホームページのデメリット 1.インターネット利用者(携帯電話利用者含む)しか閲覧できない。 2.パソコン、インターネットに関する多少の専門知識が必要。 3.更新、掲示板・メールへの返信等、管理に手間がかかる。 ホームページの作り方 1)HPとは何なのか。初心者向けの本やHPをみて研究する。 (参考HP) とほほのWWW入門 http://tohoho.wakusei.ne.jp/www.htm ↓ 2)HPの概要を考える (タイトル・コンセプト・レイアウト等々) ↓ 3)実際に作成する。 ・タグをテキストに実際に書き込んでいき作成し、 インターネット上で見られるように設定する。 ・ホームページビルダー等の作成支援ソフトを使用する。 ・無料HP開設サービスを行なっているところには、 「ホームページ作成ウィザード」があり、その流れにそって、 HPを開設することが可能。 (参考HP) ジオシティーズ http://www.geocities.co.jp/ hello http://www.hello.co.jp/ ↓ 4)HPを宣伝する。 ・知り合いに教える。 ・検索エンジンやHP紹介メルマガに申し込む。 ・HPを持っている人同士でリンクをしあう。(相互リンク) (参考HP) PRJAPAN http://www.prjapan.co.jp/ 一発太郎 http://ippatsu.net/TARO/
○ 画像を多用すると表示が遅くなる。 使用を抑えたり、減色したりして、表示の速度を高めよう。 ○ 適度な大きさと色使いで、レイアウトを工夫しよう。 大きすぎる文字は、丁寧さに欠け、信用度をなくす。 小さすぎる文字は、読む意欲をなくす。 ○ HPは、できるだけ更新しよう。 更新していないHPはどんどん廃れていく。 日記も、週1回は書くようにしよう。 |
| うえへもどる▲ |
| メールマガジン |
メルマガってなに? 読者へ、電子メールを利用してとどけられる読み物。 それがメールマガジンです。 (「月刊ウメザワ」はその一例です) ◎メルマガのメリット 1.地域も年代も超えた、全世界の人たちへ情報を発信できる 2.パソコン上で作成したデータを印刷せずに配信できるため、 時間の節約でき、経費が抑えられる。(読者へ無料で配信できる。) 3.伝えたい情報をリアルタイムで配信できる。 4.まぐまぐ等の配信サービスを利用する場合、読者の個人情報が 発行者に伝わらないため、購読がしやすくなり、読者数が増える。 5.読者からの感想・意見が直接メールで届くようになる。 6.メルマガ発行者同士のつながりもうまれる。 ◎ホームページのデメリット 1.インターネット利用者(携帯電話利用者含む)しか購読できない。 2.内容が飽きられたら、簡単に購読を解除される。 3.パソコン、インターネットに関する多少の専門知識が必要。 メルマガの配信方法 1.自分のメーラーから、BCC等の機能を使い読者へ直接送る。 (読者のメールアドレスを把握している必要があり、 配信も手間がかかるため、小人数むけです。) ※「月刊ウメザワ」はこの方法で、約60人に送っています。 2.配信サービスを利用する。 (多少、パソコンに関する知識が必要ですが、 最善の方法だと思います。) (主な配信サービス会社) まぐまぐ http://www.mag2.com/ Pubzine http://www.pubzine.com/ melma! http://www.melma.com/ Macky! http://macky.nifty.com/ メルマガ発行までの手順〜まぐまぐの場合〜 1)メルマガの概要を考える。 (タイトル・コンセプト・テーマ・発行日・レイアウト等々) ↓ 2)メルマガ概要のHPを作成する (1ページでもOK) ↓ 3)配信サービスに、発行申請をする ↓ 4)許可がおりたら、いよいよ発行!
○ 罫線や記号を使って、見やすいレイアウトを心がけよう。 一列半角70文字前後にし、改行を多くする。 ○ 文字化けしやすい「機種依存文字」は使わない。 機種依存文字の例
○ 発行者のキャラクターを明確にすると、親しみやすい。 |
| うえへもどる▲ |
| コミュニティの場 |
ホームページやメルマガを運営する場合、知り合った人たちと より仲良くなるために、掲示板やチャット、メーリングリストを 活用すると便利です。これらの仕組みをCGIといいます。 掲示板 インターネットの井戸端会議室みたいなものです。 好きな時間に、誰もが閲覧でき、書き込みもできます。 (会員制の設定も可能) チャット ある一定の時間に、不特定多数の人が集まり、ネット上でおしゃべりを することができます。 同じ時間に集まることにより、リアルタイムで相手とやりとりが できるのが、掲示板との違いです。 会員の定例会等にも利用できます。 メーリングリスト 複数の人たちで、メールを配送・受信しあう仕組みです。 これで、メルマガを配信した場合、受信者が意見等を 返信した場合は、登録者全員にそのメール内容が配信されます。 (CGI関連HP) KENT WEB http://www.kent-web.com/ CGIZOO http://www.i-say.net/cgi/ ネットサーフレスキュー[Web裏技] http://www.rescue.ne.jp/
○ 掲示板に、書きこみがあった場合、必ず返信を書こう。 書いた人は、必ず返信を見にくる。常連もつきやすくなる。 管理者が定期的に、書きこみ、話題も提供しよう。 ○ マルチ商法等のサイドビシネスの書きこみが入ったら即削除しよう。 イメージが悪くなるだけでなく、ほうっておくと、 そういう書きこみばかり入るようになる。 ○ チャットは、毎週何曜日何時からと、日時を決めると、 人が集まりやすくなる。 |
| うえへもどる▲ |
| 電子出版 |
今まで、紙面に印刷していた内容を、デジタル化した状態で発行し、 読者がパソコン上で読めるようにした出版方法です。 電子出版の種類 ・PDF 版下作業に使われているDTPソフト等で作られたデータを、 レイアウトを保持したまま、他のパソコンでも 閲覧・印刷できるようにしたファイル形式です。 PDFファイルを読むためには、Acrobat Readerが必要です。 これはAdobe社のHPから無償でダウンロードできます。 パソコン雑誌の付録のCD−ROMにも収録されています。 PDFファイルを本格的につくるには、Adobe Acrobatが必要です。 簡単なものなら「PrintToPDF」(Mac版シェアウェア、20ドル)でも つくれます。 (参考HP) James W. Walker氏のサイト http://www.jwwalker.com/pages/pdf.html ・CD−ROM(電子本) Wardなど普及しているアプリケーションのファイル形式や、 テキスト形式のファイルを、CD−Rなどで焼き付けて配布します。 ・テキストファイル 小説や詩などの作品をHPで一部分、公開し、希望者に、 小額を支払ってもらった上で、作品のテキストをメールにて 送る手法をとる人もいます。これも電子出版といえるでしょう。 (参考HP) DreamBookClub.com http://dreambookclub.com/ 作家が公開した作品に、100冊の購入予約読者がでた場合、 書籍として出版が可能になるHPもあります。 青空文庫 http://www.aozora.gr.jp 文芸作品を中心に、電子データ化した書籍を公開している サイトです。 |
| うえへもどる▲ |
| あとがき |
| インターネットは、お金がなくても、無名でも、自分の作品が発表できる場です。 年齢・地域・立場をこえた心の交流も生まれます。 文字による表現方法がメインになるため、言葉の使い方には注意しましょう。 匿名性が高い場だからこそ、自分にも相手にも正直になり、 謙虚であることが大切だと思います。 みなさん、ひとりひとりに、よりよいインターネットの活用法が 見つかることを願っています。 最後まで、お読みいただき、本当にありがとうございました。 (futaba) |
| うえへもどる▲ |